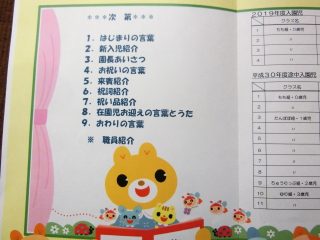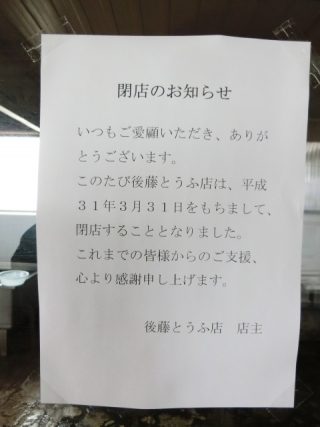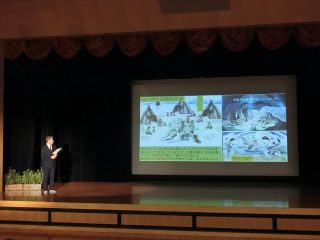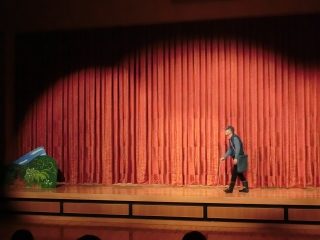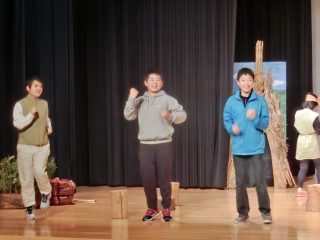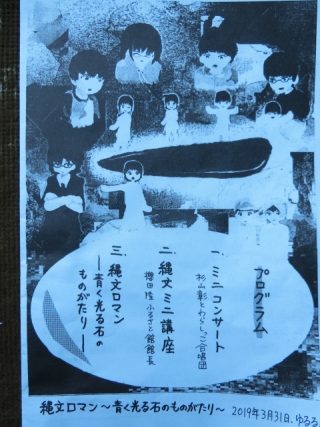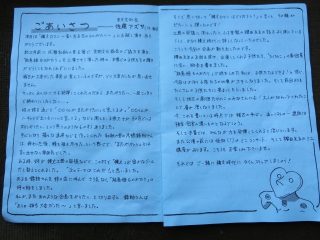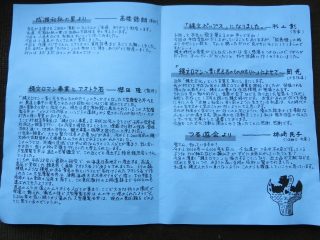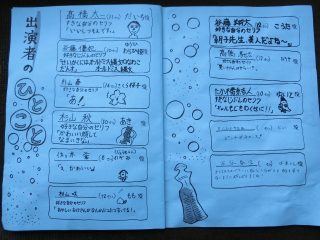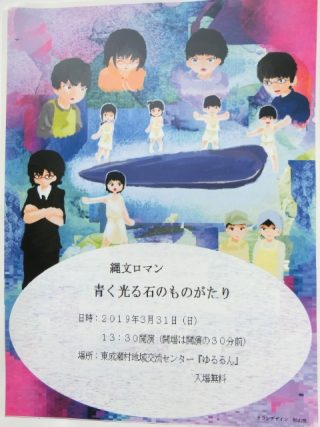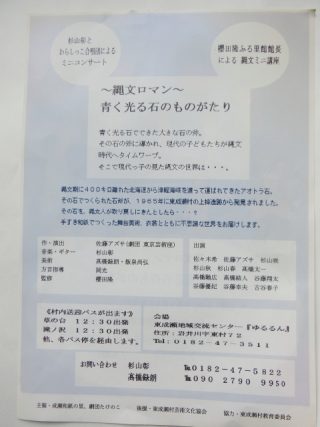秋田県は4月1日から渓流釣りシーズンに入りました。
村の成瀬川は、本流、支流ともに太公望たちの人気を集める川。解禁にあわせて岸辺の残雪には釣り人の歩いた足跡がいずこにもみられるようになりました。
そろそろ堅雪も本格化してきましたから、お天気がよければ河川敷を散歩するには絶好の雪状態となりました。先日の朝、その堅雪渡りをしていたら、成瀬川の本流で釣り人発見。

 少しのよもやま話をしながらシーズン入りしてからの釣果などをお聞きしたら「まだ、あたりが、あまりよくない」と言われました。私は釣りのことはまったくわかりませんが、今年は寒さも続き、雪解けも遅いので、それも釣果と因果関係があるのでしょうか。
少しのよもやま話をしながらシーズン入りしてからの釣果などをお聞きしたら「まだ、あたりが、あまりよくない」と言われました。私は釣りのことはまったくわかりませんが、今年は寒さも続き、雪解けも遅いので、それも釣果と因果関係があるのでしょうか。
それとはまた別に、支流とちがい、昨年の本流は上流部ほど泥の沈殿長期化もみられたようですから、それも魚たちの生息環境になんらかの影響があったのでしょうか、少し気になるところです。
成瀬川は、流量が多くかつ清い流れとしては県南部有数の渓流。渓流釣りの方々のみならず、村民歌にも、校歌にも、ふるさとの歌~悠久の風にのせて~でも歌われ村民が誇りとしているこの清流ですから、魚たちはもちろん、村の人々も通常ではない濁りにはみんな敏感です。