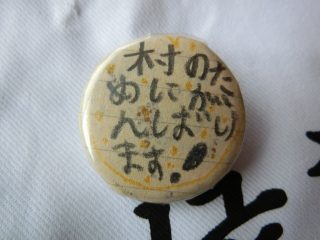時間が経つにつれて晴れ間がさらにひろがり、空の青さも色濃くなった。林、雪、青空の調和のとれた景色の中を、登山道など関係なく自由自在に歩く。これが春山雪上歩きの最も快適なところ。
岩手側のブナ林だけでなく、秋田側明通沢の県境部伐り残されたブナ原生林もすばらしい。
まだ芽吹き前で視界が遠くまで効くので、2つに大きく分かれている明通沢の広大さ、沢の深さも、春山の街道尾根を歩けばよくわかる。ほんとに広く深い沢なのである。
帰りの林内、枯れたブナの幹がある雪上に何かが落ちている。よくあるノギウヂ(脱け落ち・エゾハリタケ)かな?と一瞬思ったが、よく見たらそれはカノガ(ブナハリタケ)の脱け落ち。
昨年初冬、最晩生のカノガが出たまま冬を越し、積雪の重みで幹から脱け落ち、4㍍ほどの積雪に埋もれて冷凍され雪消とともに姿を現したのだ。途中では傘肉の厚い極上のユギノシタキノゴ(エノキタケ)もお出ましで、それもいただき。
沼又地区の荒沼では、簡易水道水源地の豊かに湧き出る清水の様子をのぞきにも立ち寄り、車到着は2時少し前。およそ7時間ほどの久しぶりの長歩きを終えた。
夕餉には、これまで食したなかでは最も食べ応えのあるユギノシタキノゴを、旬のヒロッコ鍋に入れて早速ごちそうになり、翌日はアザミやコゴミの新芽とともに脱け落ちの天然冷凍カノガもおいしくいただいた。