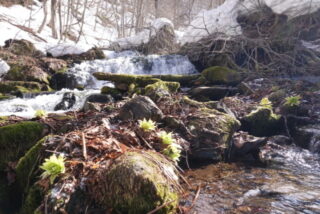ずっと以前に読み、棚に並べてあった本を取り出して再読することが多いのは、3月~4月にかけての季節だということを先に記していた。
夜がそんなに冷えなくなった今は、棚をながめて図書選びをし、寝床でのそんな愛読書の読み返しの日々が続いている。
昨日は、1991年7月に発行された「ヒトは狩人だった」(福島章著・青土社)に目がとまりふたたび手がのびた。
東大医学部卒で精神医学を専攻する著者は、犯罪者の精神分析の識者として著名な方である。なぜこの著書をまた読もうとしたかということだが、それは、日々生々しく報道されるロシアプーチン政権によるウクライナ侵略と市民への無差別殺戮行為と無縁ではない。
一般社会では、どこの国でも発生する個別の殺人犯罪も絶えない。一方で、戦争という行為、とりわけ侵攻・侵略戦争は言い換えれば「国家による、国家の名を借りた大量殺人行為」だが、その国家による殺人(はじめと最終の行為判断は個人)もいま現にみるように世界の歴史では絶えない。
人間をそのような「戦争犯罪」と呼ばれる残虐な行為にまでさせるのは何か。あるいはこれまで世界の歴史でおきた「粛清」や「弾圧」による大量殺戮行為や国民への抑圧が専制政治の手によってなぜ繰り返しおきるのか、これは、民主主義の有無や社会体制論だけでない分野でももっと研究が進められてよいことではないかと思うからである。
その点で、「ヒトは狩人だった」は多くの示唆をそこから学ぶことができる著書のひとつと思っている。福島氏は、この著書を序章の「人間の由来」から書き始め、第1章の「殺人者の攻撃性」から終章の「人類の行方」までを述べ、著者はそのあとがきで、
「………。しかし、私は、場合によっては大いに『倒錯的』ともなりうる人類が、この倒錯の能力の故に、将来この攻撃性の適応を誤って自らを絶滅させることがないことだけを祈って、この小考察を終わることにしたい。ヒトは、生き延びているかぎり、環境のいかなる変化にも適応する力がついてきていると思うのだが、もし核兵器などによって絶滅してしまえば、数百万年のヒトの進化の歴史も、すべては無に帰するであろうから。」
の言葉でこの著書を結ばれている。
1991年、今から30年ほど前に記された言葉だが、さらなる残虐性が証明されつつあるロシア・プーチン政権の戦争犯罪性を濃く帯びた行為を知る度に、殺人とヒトの攻撃性ということで、この著書に含まれる内容は人間社会への重い問いかけをもつ言葉ととらえている。