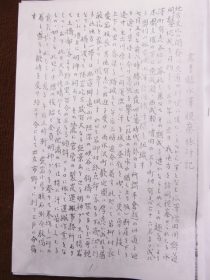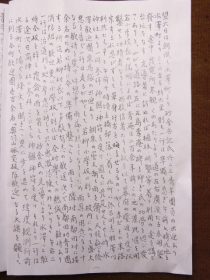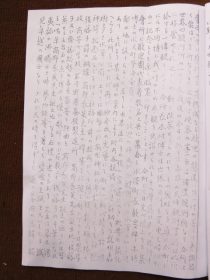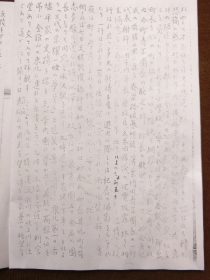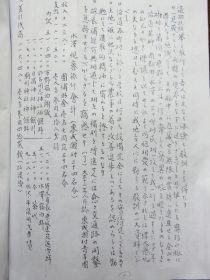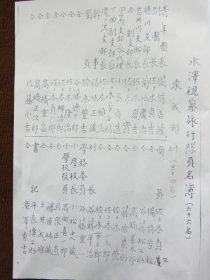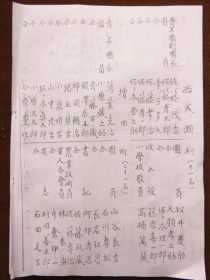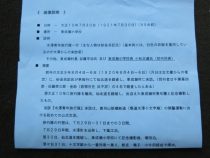両眼の手術後、1年間にわたって点眼治療を受けていたが、主治医さんから「少し、気になるところがあるが、まずよいでしょう」との診察で眼科通いをようやく終えた。
「翼状片」という眼の病で、原因としては紫外線の浴びすぎなどがあげられている。仕事でも趣味でも、子供の頃から現在まで、山と雪上でのうごきが多く、しかもサングラスを使わなかったので「紫外線が原因」にはうなづけるところがある。
2回にわたる短時間の手術で「翼状片」は切除され、ひどかった乱視もほぼ正常になったが、老眼だけは相変わらずで、眼鏡なしでは本も新聞も読みにくいままだ。
「外出時にはサングラスを」と、これまでかけたことのないほど私にしては高価なサングラスを眼鏡屋さんでこしらえプレゼントしていただいたが、治療が終われば眼のことはいつの間にか忘れてしまい、サングラスは車のダッシュボードにおさまりっぱなしがつづいている。「病治りて医者を忘るる」のいい類いである。
私の老化は、手術にあうほどのことという部位ではまず眼からきて、それは一時の補修をした。これから先、今度はどこに老化のあらわれ、医師のお世話になるところが出てくるのか、頭か、足か、腰か、内臓か、それとも……などと、そんなことが気になってきてだろうか、山科正平氏(北里大学名誉教授)著の「新しい人体の教科書・上下(講談社)」をいましょっちゅう眺めている。
眺めているというのには理由がある。これは文字どおりむずかしい教科書だからである。それで、文章のわかるところだけをひろい読み、カラー図解のわかるところだけを「眺め」るわけである。眺めるだけしかできなくても、これは、老化そして病が避けられないだろう自分の体を知るうえでとても参考になる。病治りて医者を忘れても、この著書だけは時々ひらくことがこの先もありそうだ。
▼きのうは農業委員会の年末懇談会へ。今年は、農業委員の公選制度が廃止され、新しい制度のもとで農業委員会業務にたずさわる方々が選任され活動している。昨年から、この制度移行にあわせた枠組みをつくるためにご尽力いただいた各位と、新たな職務につかれたみなさんへ感謝を申し上げ、挨拶の一言とした。