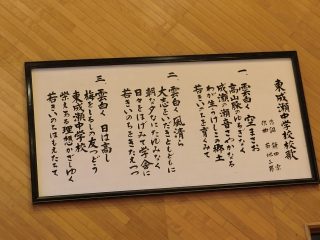23日(金)は保育園の卒園式。
今年の卒園児は15名。卒園証書を手に「僕は、私は、00になりたいです。」と大きな声で人生最初?の公への夢発表。目を潤ませている母親、笑顔の母親へ「おいしいりょうりをつくってくれて、ありがとう」等々とお礼をのべる場面。そして「さよなら ぼくたちのほいくえん」の合唱には、こちらも、毎年のことながらジーンと胸にくるものがあります。 「消防士になりたい」、「警察官になりたい」、「アイドルになりたい」などなど。時代がかわっても変わらぬ子供の人気の的となる対象もあれば、時代をうつす「なりたい」対象もあり。まったく純な夢言葉をきくのもいいものですね。
「消防士になりたい」、「警察官になりたい」、「アイドルになりたい」などなど。時代がかわっても変わらぬ子供の人気の的となる対象もあれば、時代をうつす「なりたい」対象もあり。まったく純な夢言葉をきくのもいいものですね。
子育てはまことに苦労が多し。それだけに、とりわけ同じ親でも母性という特有の愛情を子に注ぐ母親と、卒園児担任(だった、もふくめ)の保育士さんの喜びは大きなものがあると会場の雰囲気から感じます。「あの子が、この子が、こんなにりっぱに育ってくれて」と、感きわまるシーンに今年も触れることができました。
「♪♪~さよなら ぼくたちの ほいくえん~♪♪」よかったですね。子たちはよく育った、そして、保護者も保育園もよく育ててくれた、ありがとう、おめでとう、です。
ところで、これまで何十年もお聴きしていてなんとも思わずにいたのですが、この歌は「ぼくたちのほいくえん」ということで、「ぼく」はありますが「わたし」がないのはどうしてなのでしょうね。歌の場合は「ぼく」に「たち」の言葉がついているということで、男女児すべてをくくるように理解できるからそんなに気にすることではないかもしれませんが。「さよなら 『わたしたち』の ほいくえん」との詞にならなかった理由がきっとあるのでしょうね。
▼24日は彼岸の明け。わが家のお墓参りはこの日が習わしで、菩提寺境内の雪の墓地に向かいました。お墓はごらんのようにまだ厚い雪の下。スコップで少しだけ雪を掘って壇をつけ、村のお年寄りのみなさん手作りの彼岸花、ローソク、線香を、みんな雪に立てて拝みました。
18日の彼岸入りからこの彼岸明けまで、そして月命日と、仏前のお膳には家族が「この冬を越してきた食べ物」が妻の手でいつものように供えられました。まもなく春本番、これからの月命日には、貯蔵された食べ物ではなく採りたての山菜料理などを供えることができるようになります。