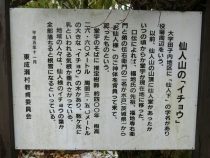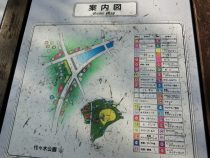去る3日のことです。役場で議会前準備の所用や打ち合わせを済ませ、帰宅して本会議再開にそなえた段取りや、各種書きものなどの原稿素案づくりに手をかけました。
手をかけましたが、外は2日続きの晴天。どうも、外に出たくて体がムズムズします。とうとう、屋内仕事を中途にして、「こんな日は、家の中で過ごすのはもったいない」と、午後の2時間ほどまた土倉沢へ向かいました。
この日は、すでに車の通った跡があるのでなんとか県境までは上がれそうと見込みました。途中には、合居川方面に向かった新しいクマの足跡が深さ20㌢ほどの積雪に見られます。予定通り県境の峠までは車で上がり、今度はさらに上をめざして歩くことにしました。
12月3日に峠まで車で上がることができて、しかも雪の上も歩けるのは久しぶりのこと。若い頃、雪上の歩きでめぐった県境(合居川と南本内川の分水嶺)の山と沢が眼前、眼下にひろがり、歩いた思い出の残るひとつひとつの林や山、沢を立ち止まっては写し撮りながら少しずつ標高を上げました。
かつて、眼下国有林の山小屋に宿泊し冬山伐採搬出をしていたわが集落の方々が、大きなワス(表層雪崩)に宿舎を直撃され命を奪われた、そのワスの発生した恐怖の急斜面が歩きの途中にはあります。また、山内三又集落の山歩きのベテランの方が、山へ上がる途中で滑落し命を失った、真冬や春山ならば思わず体が縮こまるほどの急斜面の崖も途中にあります。この山は、そういう遠い過去の2つの惨事を頭におきながらの歩きとなります。
標高を上げるにつれ積雪が多くなり、膝の高さを上回るほどになりました。ほとんど雪に足が沈まないノウサギの跳ね跡が雪上にはいっぱい。しかし、こちらはカンジキを持たずの山入りなのでそのままでの長い歩きはムリ、それにきつい斜面に積雪が増していれば見えない箇所からの雪崩の危険もあり、上がろうとしたヒヅヅ(ツルクラ沢)上部の尾根地点までは行かずに引き返しました。
権四郎森(ゴンシロウモリ・南本内岳のこと)やサンサゲェ(三境・三界山のこと)、南の森、それに目の前にでんとホンネェガアリス(蟻巣山)があります。それらを一望し、「来年春は、久しぶりにこちらから県境を歩き、三界山、胆沢川方面を周回する残雪山歩きを」と心に秘めました。
この日歩く途中で目にしたのは、ブナの幹にとまっていそがしそうにうごきまわるシジュウカラの仲間の群れと、人なつっこく目の前に飛んできたミソサザイ。それにナナカマドとヌルデ?かウルシの類いの実。ほんとはいちばん目にしたかったクマさん、それにもしかしたらと期待していたクマタカ、イヌワシ、ノウサギとの出会いはなし。でも、今後の山行のために山全体の様子を確認し写真にも記録できたので、まずは満足の歩きでした。
▼議会の一般質問通告はきのう正午までに4人の議員からありました。11日の本会議までに一定の日数がありますから、質問する側も、答弁をする側も余裕をもって準備をすることができるでしょう。