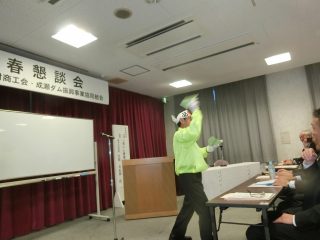豪雪対策本部が設置されたということもあり、きのうは成瀬川最上流部集落の菅ノ台まで雪状況を視に向かいました。
今は仁郷や桧山台の集落はなくなったので、大柳地区が村の最深積雪の集落。その菅ノ台集落は県内で最も雪の深い人里のうちのひとつということになります。
椿台橋より向こうの路線は昨年までと同じように国道除雪もよく行き届いています。ロータリー除雪車(吹き飛ばし)が適宜出動したすぐ後にローダー除雪車もすかさず対処されていて、路上に残った雪がすばやく処理され、機能的な除雪がなされていました。写真は菅の台に向かう県道です。
先日の豪雪対策本部の会議で発言のあった椿台橋より下流部の国道路線については、その実情が関係当局に伝えられたでしょうから、改善されつつあると思われますがどうでしょうか。その箇所は路線延長が長く、さらに障害物などもあって作業に手間取るのに、その割にしては「除雪態勢」が弱いのではないかという声もこちらに寄せられています。要するに必要な態勢が確保できなくて「手薄」ということなのか、そうであればそれにふさわしい対応策が求められるでしょう。「手薄」であれば作業にあたる労働者のみなさんが一番大変ということにもなります。
夏秋トマトが栽培される大柳・谷地地区のビニルハウスは、雪害を防ぐための農家の懸命な除雪作業の跡がうかがえます。ハウスは雪国対応の骨組みですが、雪に埋没させればそれでもたちまちのうちに雪の圧力で折り曲げられてしまいます。なので、損傷させないための努力が必死になされている様子です。
菅ノ台集落は冬期間に空き家となった家が増え、現在ここに年中暮らしている方はたしか3世帯となってしまったようです。積雪ほぼ3㍍近いと推測される小さな台地にも、この寒波でさらに激しく雪は降り重なっています。
川の様子は、厳寒の草ノ台橋近くの成瀬川です。これからは本流、支流ともに1年間で最も流水量が少なくなる時です。これから一月は豪雪との向き合いが続きます。お互い様の心で水をみんなで有効に使い合うよう協力がもとめられるでしょう。