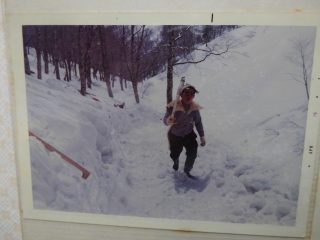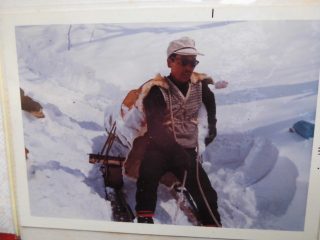きのうは村議会常任委員会の新規起業に関する調査活動が午前に、午後は村内の雪状況視察がそれぞれ行われ同席、同行しました。
雪状況の視察では、雪と関わる生活道路の改良、ほぼ管理放棄とみられる空き家や雪下ろしがまったく不十分で危険な住家、道路の落雪危険箇所や見通し不良箇所、道が凍って車両が滑り危険な箇所、雪の重みでゆがんだ菌床しいたけハウス、ウルイ畜舎の屋根雪による軒の損壊箇所や雪崩危険箇所などを視察しました。
雪下ろしや当面の落雪防止策など、早急に行動をおこさなければならない課題もあり、それらは視察後の講評で議員各位から「対策を急ぐべき」旨の発言がありました。
会議を終え帰宅途中に携帯電話が鳴ります。なんと、いましがた視察し「早急な対策をとるべき」と話し合った国道の落雪危険箇所に「今、雪が落ちている。危なかった」と同僚議員からの連絡です。
早速現場に向かい確認。走行車線直下への落雪で「小さい車なら危なかった」とその落雪の上を通ったばかりの同僚議員が語った言葉通りの様子です。写真(最後から3枚目が雪が落ちる前の午後2時42分の視察時の様子。最後から1枚目と2枚目が同じ現場の落雪した後の午後5時21分の様子)のように現場を見れば危険は瞭然で、車への直撃でなくて幸いでした。こういうことが過日にも起きていたので「関係機関による早急の策を」ということがこの日も語られたばかりだったのです。
2月半ばまでは積雪深が最大にむけて更新される年が少なくなく、今日からしばらく厳寒の戻りも予報されています。気のついたことは早くお互いに伝え合い、今後は事故なく春を迎えたいもの。警戒と備えをゆるめずにもうしばらく気をつけあいましょう。
▼夜は、先に全家庭に配布された村のハザードマップ(案)について、調査を行った県と関係事業会社、村による説明会があり出席。ご説明をお聴きし、土砂災害の危険箇所について「地質上の特徴をよく調べて、一律でない注意喚起の方策」などを、地元の過去の山地土砂崩落の事例を引きながら求めました。