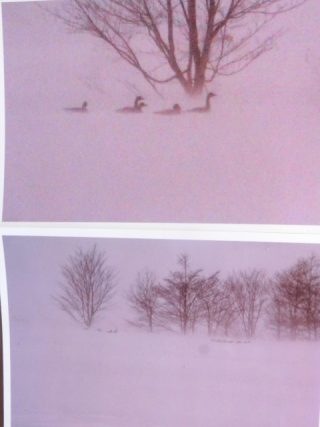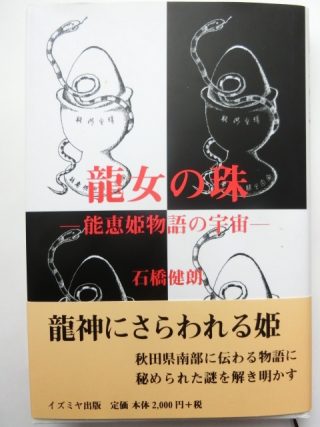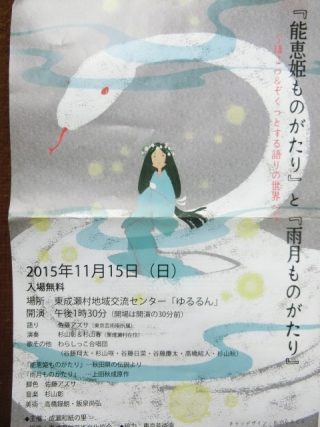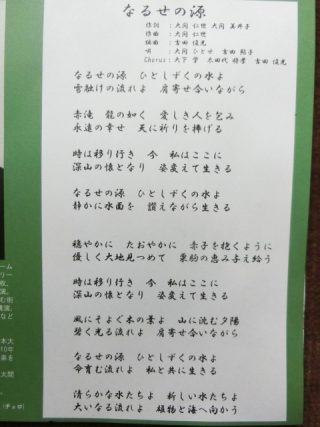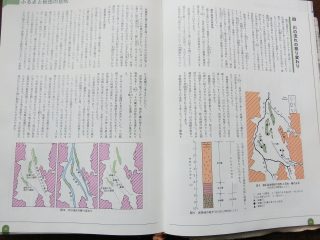立春の今朝、我が家まわりで20㌢ほどと久しぶりの積雪となり除雪トラクターを動かしました。ここ2,3日の大雪も予報されましたから、雪降りを待っている方々にとっては「願ってもない積雪」。
かまくらや犬っこまつりらしい雪景色のなかでの小正月行事ができることに関係者はホッとしているでしょう。しばらくは冬らしいお天気が続くようで、春4月並の異常な冬はこれで終わりかもしれません。
きのうもまたまた雨で、少し積み重なった雪はたちまちのうちに薄くなりました。なので、今日もまず雪の少ないきのうまでの様子を記録としてのこしておきます。今朝は、また白が支配する村に戻りましたからね。
今日とりあげるのは、わが集落と椿川手倉地区を結ぶ川通りの崖にある硯滝(すずりたき)。
ここは、蛇行する成瀬川が長年かけて削りとった崖です。
春は萌える若葉、秋は紅葉と、村の里山景観のひとつにあげられる美しい小さな崖地。そこにあるのが硯滝。滝の上部すぐから、わずかの水が湧き流れ落ちるので、細々の水ながらも滝の名がつけられたと思われます。
村の郷土誌は、集落の歴史を記す一節の岩井川の叙述部で「秋田風土記」を引用しています。「風土記」は、「此里手倉との間に硯石を生す、川岸の山なり至りて難所なり、其所の石を取て作る、名を鹿通石と云、硯石のあるところは滝の下也、(以下略)」と記します。滝が滑り落ちる岩はその硯石となった材料と同じなのでしょうか。
その硯滝も、いつものこの季節なら雪と氷にほとんどが覆われていたでしょうが、今冬は雨で水量もやや多く、滝全体が姿を見せていて、ここもまるできのうまでは春4月のよう。
そばには、葉緑の濃いヒメアオキも雪に押さえられずにいきいきと暖かい冬を越しています。今冬は、同じように常緑で背の少し高いユキツバキも、村の各地でやはり雪に押さえられずにシャンとしています。それよりずっと背が低くかよわいヒメアオキもこのとおりなので、豪雪の村は、土肌だけでなく、かってないほど緑も多く目にはいる異常な真冬です。