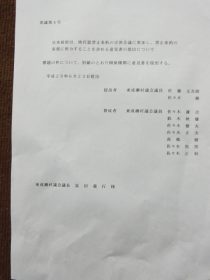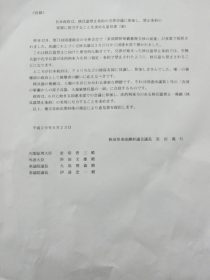夏の渓流釣りシーズンなのでしょう、我が家前の成瀬川には、休日となると釣り人の姿が絶えなく見られます。
夏の渓流釣りシーズンなのでしょう、我が家前の成瀬川には、休日となると釣り人の姿が絶えなく見られます。
イワナも釣れればヤマメも釣れる、それに極上の鮎も釣れるということで成瀬川は太公望たちに人気の的。今年は深山の雪解けが遅く、川の水量は安定しているようですが、釣りということでは魚たちにどんな影響がある年なのか、釣りには門外漢の私も、そんなことへは関心があります。
食べる、獲るということで、渓流魚の中で私が最も好きなのはイワナでもアユでもなく、それはヤマメ。あの銀色の体をした大きなヤマメ、天然ヤマメはしばらくの間ごちそうになっていないので、今年は童らといっしょになって「獲る、食べる」を夏のひとつの楽しみにしています。