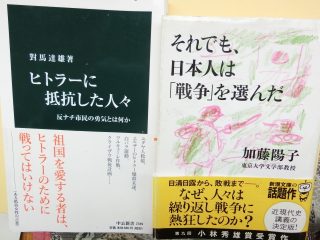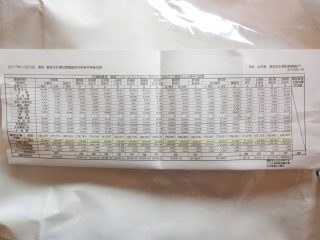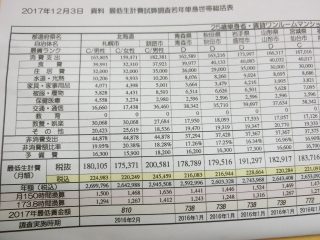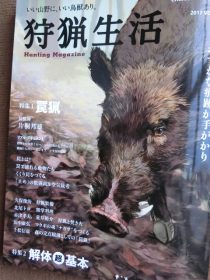ためていた書類などの整理をしながら、一年でもっとも読書の時間がとれる日々をも過ごしています。そのためにいくらかの本の買いだめもしているのですが、とくに目を通しているのは一度か二度読んでいて、「さらに、もう一度」と、繰り返し手がのびる著書です。
先日、NHKBSテレビは、第二次世界大戦当時、中国大陸にあった旧日本軍731部隊の特集番組を報じました。内容は、戦争のなかで捕らえた侵略地の人々に対する同部隊の「様々な人体実験」について、「悪魔の行為」ともいえる非道の事実を知らせるものです。
私は、人体実験の対象にされた「マルタ」とよばれた人々の無念さへの情とともに、731部隊の幹部の方(軍医を含む)が、再生された裁判の録音テープのなかで、自らが冒した非道の実験について涙を見せ痛恨の反省をする、人としてのあるべき本来の姿に胸がしめつけられました。部隊のうち幹部の多くは、戦後の国際裁判でも罪が問われず、国公立大学医学部等の教授や薬剤会社への職務につき戦後を生きたことを放送は伝えました。
実は、それとはかなりちがいますが、あの戦中、満州への開拓移民などが全国から募られたという歴史がわが国にはあります。満州へはわが村からもむかっています。敗戦時にはこの移民のみなさんが大変な状況におかれ、わが湯沢雄勝地方でも多くの方々が犠牲(集団自決もふくめ)になった惨状が毎年報道されます。
この移民策でやはり多数の人々を満州へ送り出した当時の長野県。そこの旧河野村(現豊岡村)村長・胡桃澤盛氏は、満州へ多くの村民を送り出し、その方々の72人が終戦の混乱の中で集団自決に追い込まれたことへの自責の念から、終戦の翌年、46歳で自死しています。わたしがこのことを知ったのは「それでも日本人は「戦争を選んだ」東大大学院教授加藤陽子著、新潮文庫」によってですが、故胡桃沢氏は、終戦直後の11月の日記で「何故に過去の日本は自国の敗けた歴史を真実のまゝに伝える事を為さなかったか」と記していることを加藤教授は著書のなかでとりあげています。この旧河野村のこと、胡桃澤氏のことが、明後日10日の日本放送テレビ「決壊」の題で10時半から放映されます。たまたま同じ日のNHKBS1でも、2時から「731部隊」が再放送されます。
戦争と人間。人間と権力争い。日本が内外で冒した大戦時の罪(治安維持法も含む)だけではなく、ヒトラーのドイツ、ベトナムや広島・長崎でのアメリカの残虐、旧ソ連や中国によるアフガンやベトナム侵攻、スターリン、毛沢東、ポルポト政権の幾百万人が犠牲となった大粛正も、みな、人間社会がうんだ出来事です。なぜ、社会は、幾度もの戦争、粛正、残虐をとめられなかったのか、止められなかったどころか、なぜ戦争や粛正に高揚したのか。未来社会を展望するうえでも、歴史の事実をよくとらえねばならず、それでも日本人は「戦争を選んだ」の前述の著書をまた取り出しました。それと、あのヒトラーが実は圧倒的に支持された歴史がドイツにはあり、そういうなかでの反ナチの運動を書いた「ヒトラーに抵抗した人々(對島達雄著・中公新書)」の著書をこれもまた取り出しました。みな、戦争と粛正の「なぜ」を知り、過ちをおかさない社会になってほしいためにです。