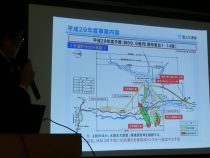朝に雪寄せをしていたら、いつもなら雪に覆われている地面がすべて露出している箇所があります。「あれっ、おかしいな」とそこの土を少し踏んだら水がジワっと滲んできます。
 そこは水道管が通っているところですから、おそらく管から水が漏れているのだろう、そう判断して土を掘り管をだしたら、やっぱり、管の継ぎ目が裂けてそこから水が噴き出しています。破損に及ぶような何かの圧力が管にかかっていたためのようです。
そこは水道管が通っているところですから、おそらく管から水が漏れているのだろう、そう判断して土を掘り管をだしたら、やっぱり、管の継ぎ目が裂けてそこから水が噴き出しています。破損に及ぶような何かの圧力が管にかかっていたためのようです。
早速水道屋さんに連絡し補修してもらいましたが、農機具が壊れたときに我が家にかけつけてくれる笑顔でテキパキ仕事の農機具屋の若い従業員さんと同じで、ここの水道屋の従業員さんもすばやくかけつけてくれて、やっぱり笑顔で機敏に補修していただきました。
業者さんや、そこにはたらく方々はあたりまえの仕事をしたということでしょうが、テキパキと、にこにこと、こちらの心配にこたえながら仕事をする姿をみて、「仕事には、こういう姿勢が大事なんだ」とつくづく思わせられました。
「同じ仕事をしていても、笑顔で機敏、お客さんに喜ばれる仕事ぶり、相手にありがたいと思われる対応ぶり」こういう姿勢は、民間の業者さんのみならず、公務に携わるわれわれもよくよく心がけなければならないことです。思わぬ水道のトラブルを通じ、水道屋さんや従業員の方から、人の心に響くしごとのあり方を学ばされたところです。もうひとつ学んだことは、たとえ少量の 水、それがたとえ湧水でなくても、「雪を解かす水の力は極めて大きい」ということ。雪と水利は集落のいまの暮らしでは欠かせぬ条件といえます。
水、それがたとえ湧水でなくても、「雪を解かす水の力は極めて大きい」ということ。雪と水利は集落のいまの暮らしでは欠かせぬ条件といえます。
▼水道のトラブルにとってやっかいなのは、凍結破損もふくめそれが雪の季節の冬に多いことです。土の上にはすでに1㍍50㌢もの厚い雪がありますから、作業の方々の苦労も雪の少ない地方の比ではないことがわかります。
ところで雪といえば、雪下ろしや車のスリップ事故などもふくめ雪国の各地でいたましい事故が今年も続発しています。
きのう、臨時の「保育士」をひとときつとめることになり、童を連れて道路脇の歩道にむかったら、かなり高くなった雪の壁が一 箇所崩れています。このような現象にともなう事故を防ぐためでしょう、昔とちがい今はかなりていねいに歩道雪壁の除雪も行われるようになっています。これらの壁もまもなく除雪される予定でしょう。こちらは、「まさか、その程度の雪壁で、危険はないだろう」程度にこれまでは甘くみていましたが、実際に崩れた場面を目にしたら、小さな子供や高齢の方だとこれはやはり少し「危ない」です。
箇所崩れています。このような現象にともなう事故を防ぐためでしょう、昔とちがい今はかなりていねいに歩道雪壁の除雪も行われるようになっています。これらの壁もまもなく除雪される予定でしょう。こちらは、「まさか、その程度の雪壁で、危険はないだろう」程度にこれまでは甘くみていましたが、実際に崩れた場面を目にしたら、小さな子供や高齢の方だとこれはやはり少し「危ない」です。
村にはすでに雪害警戒部が設置されています。寒中の底雪崩も急 斜面の一部でみられ、山では表層雪崩もおきているでしょう。屋根雪対応もふくめ、雪の怖さへの油断なきよう備えをしっかりしましょう。雪で気がかりなことがあったら、とにかく部落か役場へ一報を。
斜面の一部でみられ、山では表層雪崩もおきているでしょう。屋根雪対応もふくめ、雪の怖さへの油断なきよう備えをしっかりしましょう。雪で気がかりなことがあったら、とにかく部落か役場へ一報を。