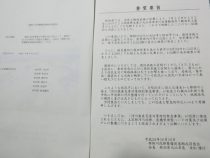山菜やキノコ採り、それに狩猟などでブナとミズナラ帯の深山に入ると、道のない尾根筋や林の斜面などで時々こんな傷跡のついた木と出くわすことがあります。
 それはキノコ採りがつけたケズリ(木印・きじるし)。キノコの発生場所を忘れないための覚え印です。マイタケなら所々にある特徴的なミズナラの木に発生するキノコですから覚え印など必要ありませんから、深山でのこの印はシシタゲ(コウタケ)の採れる場所を暗示したものでしょう。
それはキノコ採りがつけたケズリ(木印・きじるし)。キノコの発生場所を忘れないための覚え印です。マイタケなら所々にある特徴的なミズナラの木に発生するキノコですから覚え印など必要ありませんから、深山でのこの印はシシタゲ(コウタケ)の採れる場所を暗示したものでしょう。
同じような林の続くブナ林ではシシタゲは土の色に似ていてなかなか発見しにくく、それでこの方はこんなケズリを刻んだと思われます。まれに、ノギウヂ(エゾハリタケ)のある場所でも、半枯れの発生木そばに同じようなケズリ跡が見られます。春の残雪山歩きで、深いブナ森の山中でこんな印に出会うと、山の特徴を見て「ほほう、このあたりの地面にはシシタゲが出るのだな」「このブナにはノギウヂが出るのだな」と推し測れます。
さて、ブナの木におそらくナタで刻まれたと思われるこのケズリ。読めば「九月二十日」とこちらには理解できます。9月20日は深山ならシシタゲの出る頃なのです。続いて屋号印のヤマの下にトの字が見られますから、集落の古老の方ならこのケズリをつけた主がどなたの家かわかるかもしれません。
こちらがこの木印を目にしたのは約半世紀近く前。ここでシシタゲを採った話を友人に昔語ったら、山に詳しいその方は「シシタゲ山なば、てぇげぇ(たいがい)、すぐそばさ、ケズリあるものだ」と教えてくれました。翌年その場所に向かい、まわりを見渡したら、あったのです、このケズリが。
それより以前から、この印を刻んだ主はここで幾度もシシタゲを採ってきたのでしょう。「形にのこる印は、自分だけでなくほかの方も知ることになるから、印はつけない」とキノコ採りプロのある方はいいます。ただし、ケズリは一種の暗号みたいなもの。その傷跡がある木からどの方角に、どれだけ離れた場所にお目当てのキノコがあるのかは、印を刻んだ方、あるいは、そこでキノコを発見した方しかわからず、やはりプロでもケズリをつける方はおられるのです。
プロなら頭だけに刻んでおく、なるほど。プロなら、簡単にキノコの発生場所がわからないようなケズリを刻む、こちらもなるほど。では、この印を刻んだ方はプロかセミプロか、それともごく普通の山人か、そんな楽しい推測も私の山歩きには加わります。

 籾すりをすべて済ませ、学習発表会の代休日となった童の手も借りてぬか(モミガラ)かたづけなども終わり、機械の掃除なども半分ほどには手をかけました。作業が終われば、また来年に備えて各機械のあれも掃除、これも掃除の日々となります。
籾すりをすべて済ませ、学習発表会の代休日となった童の手も借りてぬか(モミガラ)かたづけなども終わり、機械の掃除なども半分ほどには手をかけました。作業が終われば、また来年に備えて各機械のあれも掃除、これも掃除の日々となります。


 畑のそばの沢沿いには、大きなシラグヂヅル(サルナシ)が幾本かあります。春に花を観た蔦の実も完熟期をむかえたので、手の届く範囲の実をもぎ取りました。触ると破れるほどに熟しきった実もあり、口にいれたら「天然のキウイフルーツ」といわれる特有の甘さが口中いっぱいにひろがりました。
畑のそばの沢沿いには、大きなシラグヂヅル(サルナシ)が幾本かあります。春に花を観た蔦の実も完熟期をむかえたので、手の届く範囲の実をもぎ取りました。触ると破れるほどに熟しきった実もあり、口にいれたら「天然のキウイフルーツ」といわれる特有の甘さが口中いっぱいにひろがりました。