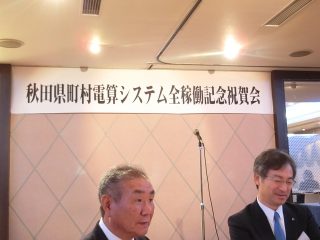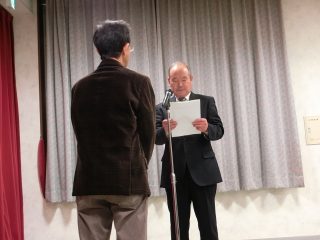過ぎた土曜日、つかの間の散策でいつもの家前の河川敷へ。
19日あたりから強い冬型の寒気が来そうなので「雪が積もらないうちの最後の散策を」とふらりと向かったら、成長しきった少々のムギダゲ(ムキタケ)やカノガ(ブナハリタケ)とともに、さあさあ、こんなに美しい輝きの晩生ナメラコ(ナメコ)がいっぱいです。






 期待していなかった出会いだけに、そのうれしいこと。あっちに寄りこっちに寄りしながらしばらく眺め、シャッターを押し押ししました。
期待していなかった出会いだけに、そのうれしいこと。あっちに寄りこっちに寄りしながらしばらく眺め、シャッターを押し押ししました。
昭和22年の大洪水までは田んぼ続きだったというここの河川敷(川と石の下には昔のたんぼ作土の層が厚くあるはず)には、県境や深山の森に倒れたブナやミズナラ、トチやイタヤの木が、洪水に運ばれ毎年どんぶらこどんぶらこと流れ着き、それらの枯れ木には多種のキノコが顔を出します(まれにマイタケも)。一方、河畔林のなかで倒れた柳やニセアカシヤにも出るキノコあり。我が家前は、いつもご紹介するように私にとって四季を通じて童たちとの遊びの楽園でもあり、魚や鳥、生きものたちとの出会いの楽園でもあり、さらにきのこと山菜の楽園でもあります。
美しい輝きのキノコだよりを載せられるのは、これが今年の最後となるでしょう。
▼最後の写真2枚は、この間も少し触れました猛毒キノコのニガクリタケです。先の写真で紹介したニガクリタケよりもこちらは同じキノコでも色がやや明るく、食タケのユギノシタキノゴ(エノキタケ)やヤマドリモダシ(クリタケ)により近い色の個体です。もっと似ている色の個体もありますから、ニガクリタケは侮れないのです。こんな小さなキノコで子供をはじめ一家の何人かが死に至ったという例も国内にはあるようです。

くどいようですが繰り返しておきます。食べた量や個人差もあるでしょうが、食べれば、ほとんど死に至る恐ろしい猛毒キノコが、食タケと似た形と色で、同じ木に並んで出ていることもあるのですからやっかいなのです。楽しさおいしさと恐ろしさ、キノコは天国と地獄からの二つの世界からのつかいのようなもの。なぜ猛毒のつかいがキノコにもあるのか、不思議なものですね。