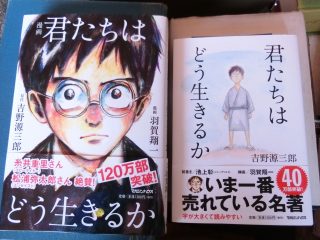土、日曜と西日本や東日本で時ならぬ真夏日となり、わが集落も26度℃の夏日。河畔林のヤナギとともに木々の中では芽吹きが一番早いブナの芽吹きが、先週末から里山で次々とみられるようになりました。
芽吹きのいちばん早いブナの葉のこの様子をわたしたちは「木の葉ホゲダ」といいます。芽吹きを「ホゲル」の言葉で表すのです。さらに村のマタギたちは昔から「ブナのホゲざげさ、クマえる(ブナの葉の芽吹きはじめた境のところに、クマがいる)」とみてきました。クマは、芽吹く寸前で膨らみきったブナの芽や芽吹きはじめの芽が大好物だからです。ブナは、実だけでなく芽もクマにとって大切な栄養源の樹なのです。
 ▼童を連れていつもの河川敷を散歩したら、コゴミも芽を出し始め、ユギノシタキノゴ(エノキタケ)もいっしょに摘み採り、待っていた初物をごちそうになりました。ほかの山菜も次々と芽を出すこれからは、初物ごちそうをいただける日々が続きます。
▼童を連れていつもの河川敷を散歩したら、コゴミも芽を出し始め、ユギノシタキノゴ(エノキタケ)もいっしょに摘み採り、待っていた初物をごちそうになりました。ほかの山菜も次々と芽を出すこれからは、初物ごちそうをいただける日々が続きます。
▼里に近い沼又沢へも道路沿いに少し歩いてみました。
 豪雪の冬でしたから雪崩によって落ち運ばれた雪の量も今年は多く、渓谷をふさぐ雪の橋はいつもの年より規模が大きく見えます。深山の川を渡る生きものたちも、登山や釣り、山菜採りで渓谷に入る人々も、今年はかなり遅くまで雪の橋を渡り続けることができそうです。
豪雪の冬でしたから雪崩によって落ち運ばれた雪の量も今年は多く、渓谷をふさぐ雪の橋はいつもの年より規模が大きく見えます。深山の川を渡る生きものたちも、登山や釣り、山菜採りで渓谷に入る人々も、今年はかなり遅くまで雪の橋を渡り続けることができそうです。
雪解けが早く進んだ雪崩跡の日向斜面や川の岸辺には、サグ(エゾニュウの仲間)の新芽が勢いよく伸びつづけています。この野草が大好きなクマやカモシカたちは、食を求めてこうした場所の近くでこれからの日々を過ごすようになります。
川沿いには、ここでもエノキタケやコゴミが、瀬の流れからはじける水しぶきを時に受けながら暖かすぎる春の陽ざしを浴びています。
そばの土手にはチャワンバナコ(キクザキイチゲの仲間)やカダゴ(カタクリ)、バッケ(フキノトウ)たちが花の競演で、ヒロッコ(ノビル)もおいしそうな新芽を残雪の中からいっぱい突きだしていました。