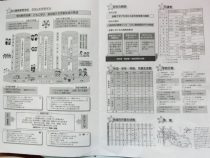このブログは、秋になると村の自然、とりわけキノコや木の実を軸にして季節の様子をお伝えしています。それで今日もあきたらずに過ぎた日のきのこ便りを載せてみました。
まず5日早朝のこと。サルナシやアケビなど木の実の写真を撮ろうと家の周囲を散策していたら、なんとミズナラの根元に大きなミャゴ(マイタケ)発見です。



深山ならまだしも、家から2分ほどしか離れていない木にマイタケですから、これにはこちらもびっくり。早速朝餉準備真っ最中の妻を呼んで「マイタケ採り」を体験してもらいました。マイタケは大小あわせて3個。老菌ですがまだ十分に食べられる姿でした。
住宅そばの栗の木などでは採られることがあるマイタケですが、まさかこんな家近くのミズナラに発生するとは思いもよらぬこと。マイタケをどこかから採ってきた時、その土着きを切り落として投げた際の菌とかが風に運ばれてミズナラに取り着いたのでしょうか。とにかくこの日は朝からうれしい出来事のはじまりです。
10月に入ればオオヒメジ(ネズミヒメジともいう、ホンシメジのこと)が採れ時となるので、5日午前の村内周りの所用を果たした後に自前の採り場に向かってみました。
そこは、ここ何十年とおそらくこちらしか向かうことのない場所。つまり、いつ行っても確実に里山のキノコの王様と私だけが出会える場所です。ホンシメジでこういう「採り場」を持つ方は、プロ、アマを問わず案外多くおられるでしょう。
そのホンシメジ、今年は顔を出すのがいつもの年より5日ほど早く、多くがすでに老菌状態で、このキノコ特有の王様らしいすばらしいかたちとはかなりかけ離れた姿をしていました。中には腐ってしまった大きな株も。今年の発生量は中の下クラスという様子です。








そばには遅出のクリカラモダシ(クリフウセンタケ)が菌列をつくっていっぱい。これは採るのも食べるのも私は大好きなキノコですので、ゆっくりと楽しみながら一本、また一本と土から抜き出し地面に並べました。地面からきれいに抜き取りやすいキノコなのです。





シシタゲ(コウタケ)も、遅くに出たのがちょうど採り頃だろうとおなじ5日に向かったら、それは予想通り。ありったけ成長した株や個体がこちらの行くのを待っていてくれました。コウタケへのこちらの評価は、ホンシメジ、マイタケに勝るとも劣らぬ王様格の威厳をもつキノコという扱いです。姿とともに、貴重種なのでそういう価値付けになります。









それをリュックいっぱいにしての帰り、クォー、クォーと頭上に聞き慣れた鳥の声が。見上げたらカギをつくり飛ぶ雁の群れです。毎年、須川温泉付近が紅・黄葉真っ最中の頃に彼らは渡ってきますから、今年もちょうどその季節になったのです。雁の初渡りが見られ、初鳴きを聴く頃には、王様格のキノコたちが終わりの頃とおぼえておけばよさそうです。