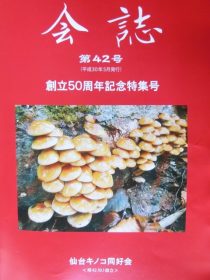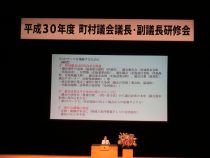議事日程のはじめに、佐々木健夫議員から提出されていた一身上の理由による議員辞職願いが議題とされ、許可されました。
佐々木議員は役場の課長職員を途中退職して現村長と連続二回の村長選をたたかい、その後には村議として連続4期目(来春4月が改選)の職務途中にありました。
佐々木議員は、健康をそこねて議会へ出席できなくなるまで毎議会の一般質問に立たれ、議案審議でも旺盛な質疑をおこなっていただきました。在職中のご活躍に心からの感謝を申し上げたいと思います。議員は辞職となりましたが、早く健康を回復なされて、今後も村発展のために、村政へのいわば「ご意見番役」として様々なかたちでご指導をお願いできればと思います。長い間のご活動ほんとうにご苦労様でした。ありがとうございました。
さて、村長選後初の議会となったきのうは、3月に骨格予算としてくまれていた一般会計にも政策予算が加えられ、村長行政報告の前段では、村長選の公約などをもとにした施政方針がのべられました。


よく6月議会は国保議会といわれるように、今年度の国保税の税率を決める条例改正案や、監査委員の選任同意案、平成30年度各会計予算の補正、同じく29年度予算の補正にともなう専決処分報告、除雪ローダ購入の財産取得案などが提案されました。
会議は、様々な理由による日程調整にせまられ、19日に一般質問、20日に各議案の議決の本会議開催となります。その間に予算特別委員会も開かれ、14日には先に提出されていた各地区要望についての常任委員会と村当局合同による現地視察も計画されました。
▼先月につづいて辞職議員が2名となり、定数の6分の1が欠員となったため村議の補欠選挙が必要となりました。選挙管理委員会により今後選挙日程が決められます。