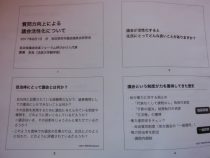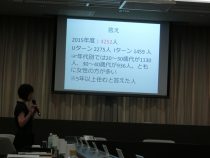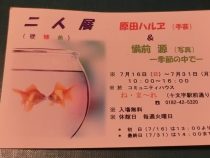今は、時間があれば、割った薪を乾燥させるために積込むしごとに汗を流しています。
 その合間に妻と母は自家用ジャガイモの掘り獲りも。熱中症への注意が呼びかけられているほどに猛暑の連日ですが、昔から、暑い夏につきものの仕事だけに、農山村の人々は「夏に暑いは当たり前」と、炎天の下、畑仕事に勤しむ姿が方々で見られます。
その合間に妻と母は自家用ジャガイモの掘り獲りも。熱中症への注意が呼びかけられているほどに猛暑の連日ですが、昔から、暑い夏につきものの仕事だけに、農山村の人々は「夏に暑いは当たり前」と、炎天の下、畑仕事に勤しむ姿が方々で見られます。





 家のまわりや里山には、先日ご紹介したタマゴタケとともに、初秋のキノコたちがやはりぼつぼつ顔を見せ始めました。まずは私の大好物のアカヤマドリ、そしてわが集落ではチンダゲと呼ぶチチタケの登場です。
家のまわりや里山には、先日ご紹介したタマゴタケとともに、初秋のキノコたちがやはりぼつぼつ顔を見せ始めました。まずは私の大好物のアカヤマドリ、そしてわが集落ではチンダゲと呼ぶチチタケの登場です。
アカヤマドリは大型のキノコですが、大きくなると傘がボソボソになったり、茎も堅くなったりで、おいしく食べられる部分はかえって少なくなります。写真のような成長度合いの頃がもっともおいしく傘も茎も全部利用できるのです。さっそくゆがいて、刺身風にしていただきました。
キノコは、地域や種類によって食文化のちがいがよくあらわれる食材で、チチタケはその代表格。ちょっした刺激を与えるだけで乳液に似た少し粘つく液がたちまちのうちににじみ出るからでしょう、名がチチタケ。とても好んで食べる県や地方があるようですが、わが村では一部の食通の方を除けばたいていの方が見向きもしない食茸です。
私は、時々、遊び心半分で食べますが、こんなにボソボソの食感はめずらしいというほどで「おいしい」という言葉はなかなか出てこないキノコです。一流の腕をもった料理人が「珍重な食材」扱いをして「すご技」で調理したら「おいしい」という感想をもつことができるのでしょうか。